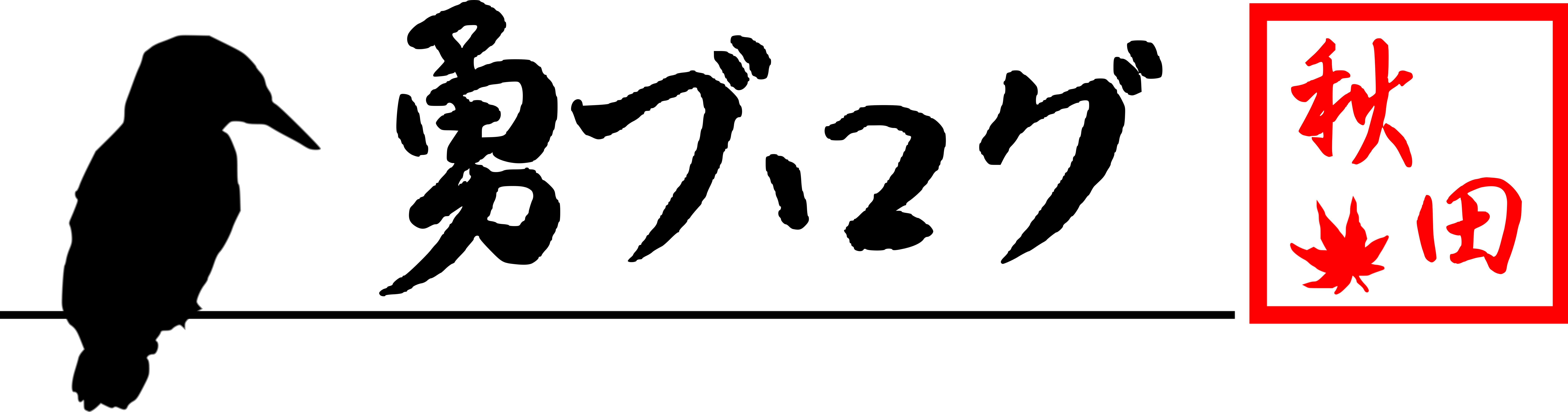こんにちわ,Isamuです。
タイトルにも記載の通り、今回はCanonのEFレンズの中で至高の野鳥撮影レンズを紹介したいと思います。
目次
解像力・描写力の良いレンズを試したい
私の野鳥撮影はTamron100-400mmレンズから始まりました。
 Tamron 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD for Canon 初めての野鳥撮影望遠ズームレンズ
Tamron 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD for Canon 初めての野鳥撮影望遠ズームレンズ
どのレンズでもそうですが、テレ端だと解像力が落ちてしまう傾向にあるのが、ズームレンズの宿命だと思っています。
しかし、野鳥撮影はテレ端で撮影することがほとんどです。
例えば、Tarom100-400mmレンズは400mmだったり、SIGMA150-600mmレンズならば600mmとほとんどテレ端にズームリングを回して撮影しています。
これまで望遠レンズはサードパーティ製から入門していた私ですが、SonyミラーレスILCE-7RM3とFE200-600mmを組み合わせて使った経験から、純正レンズなかなかいいんじゃない?と思うようになっていました。
そして、Canonで純正の望遠レンズを探して行き着いたのが、このEF100-400mm F/4.5-5.6L IS II USMレンズでした。
焦点距離はこれまでTamronレンズで使用経験があり、これまでと同じ感じで撮影に使えるだけでなく、純正レンズの使用感を直に感じられると考えました。
特に、焦点距離400mmのテレ端でどんな写真が撮れるのか、ワクワクでなりませんでした。
EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USMについて
レンズを触った率直な感想として、レンズ径がずいぶん太いな、その一言に尽きます。
CanonのLレンズの特徴の白色ボディに、レンズフードは黒色の着脱可のねじり込み式です。

レンズ重量は、三脚座を除き1,570gとやや重く、この焦点距離の望遠レンズからして図体のでかいレンズであるとの認識です。
レンズスイッチは、フォーカスリミッター、AF/MF切替、手ブレ補正のONOFF切替、それから手ブレ補正モードのスイッチが備わっています。
あと、ズームリングのトルクを調整できるトルク調整リングはかなり重宝しています。
Tight側に回すと、ズームリングを回す際にそれなりに力を入れて回さないといけないです。一方で、Smooth側に回しておくと、ズームリングが軽やかに回り、それほど力をかけなくてもズーム可能です。
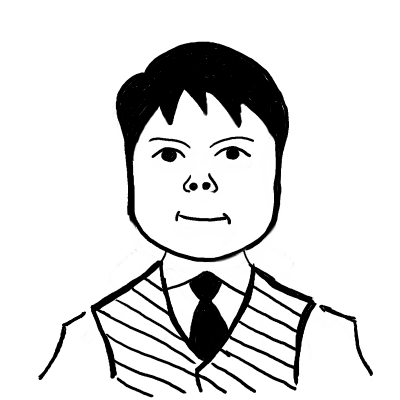 Isamu
Isamu
このリングを回すトルクを調整できるのは、これまで触ってきたレンズの中でも初めてだったので、素直に感動しました。
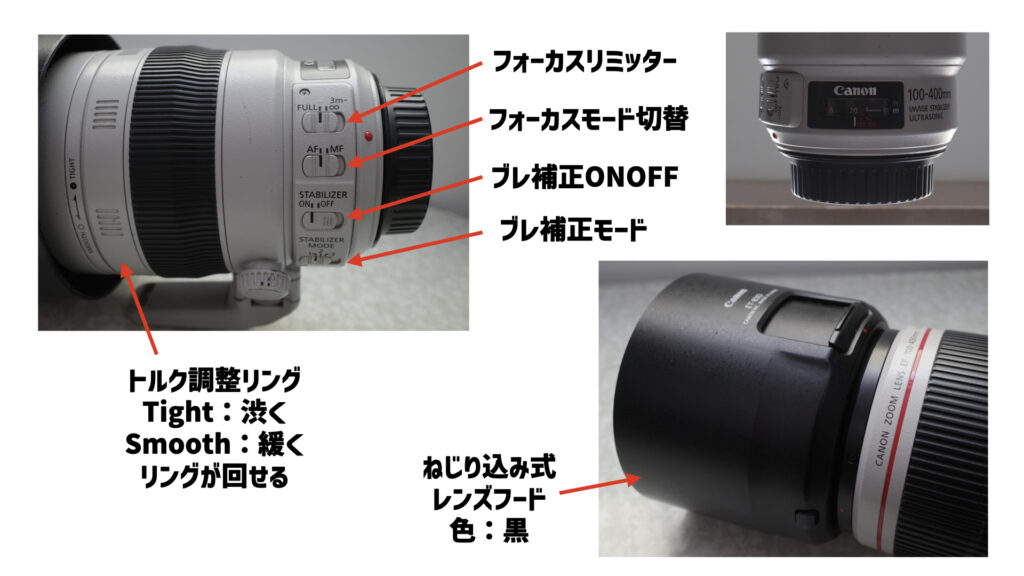
Canonのレンズの中で、蛍石を使っているレンズは描写力が高いと、そこらかしこから噂を聞きます。
レビューでも絶賛されているので、蛍石が入っているこのレンズで撮れる写真が楽しみで仕方ありませんでした。
EF100-400mm F/4.5-5.6L IS II USMレンズには、蛍石レンズが1枚使用されています。
作例紹介(野鳥写真)
春先の都市公園でジョウビタキを撮ってみました。
下の2枚はいずれもテレ端の400mmで撮影しましたが、撮ってみてテレ端の解像力すごくね?と素人目線でもわかるほどくっきりはっきり撮れていました。


地面に降り立ったいるツグミを撮ってみました。

撮影距離が近ければ近いほど、その進化を発揮するこのレンズ。
毛の一本一本まで解像し、私なんかの腕でもこれほどの写真が撮れるのかと感動です。

市街地のお池でカワセミを撮りました。
天気の良い日で春らしさを感じさせる一枚となりました。

飛びものもまだうまく撮れないながらも、ちゃんと撮影できそうです。

ダム湖を飛翔するヤマセミです。
飛びものは撮り慣れていないので、反省が多いです。

はじめての出会いで興奮していたせいか、ピン甘だったアカショウビンです。

雪深い山々の麓の山村で撮影したアオゲラです。
雪が降っていたので、ピンと定まらず。。。

ピン甘が続きます。
ベニマシコの飛翔です。紅色きれいですね。

カケスも残った木の実をせっせこ運んでいました。

市街地から遅れながら里山でも桜が開花しました。
この写真は逆というわけでなく、ヒヨドリが逆さまになって蜜を吸っていました。

これは…オオルリ?だっけか
カラフルな体毛の♂と地味めな配色の♀の野鳥は意外と多く、どの鳥だっけか?とわからなくなってしまいます。

ある程度距離が離れた位置にとまるノスリもこんな感じで撮れます。

瓦屋根にとまっていたムクドリです。

ダイブ後、魚を捉え浮上してきたカワウ殿です。
シャッタースピード1/2000secまで速めれば、野鳥の生き生きした姿を撮影できます。

どこかを見つめるアオサギです。

春の渡り直後、都市公園で滞在していたキビタキです。

太い木にベスポジだったシジュウカラです。

至近距離からコムクドリ殿。
距離2m以内と完全に運で撮影できた一枚です。

レンズ使用感や撮ってみての感想
レンズ径がやや太いので、手の小さい私にはレンズを持つにはちょっと大変です。
レンズ重量も1,570gとそれなりに重いので、100-400mmの焦点距離を持つ望遠レンズにしてはゴツメのレンズだな改めて認識しました。
レンズ全長は極端に長いわけではないので、取り回しは難しくないですが、このゴツいレンズを振り回すのには慣れが必要かと思います。
また、望遠撮影時におけるブレの抑制にも気を配りたいところです。
手持ちでEF100-400mmレンズは使えるとも、一脚を使って安定させて撮影するなど、工夫を凝らして私は撮影しています。
前述の通りですが、テレ端の解像力は目を見張るものがあります。
正直、このレンズのテレ端で撮った写真をPCで見たとき、「なんだこのレンズすげぇ!」って驚きました。
このレンズは中古で20万もしないで購入できるレンズなので、今はミラーレスでRFマウントのレンズも販売されていますが、まだまだこのレンズは現役間違いなしです。
まとめ
EF100-400mm F/4.5-5.6L II USMレンズは、望遠ズームレンズをいくつか扱った経験のある私からしても、テレ端の解像力が素晴らしく、野鳥撮影にぴったりの望遠レンズだと太鼓判を推します。
周りからの評判も良く、まさに至高のレンズと言っても過言ではないでしょう。
RFシステム(Canonミラーレス)が主流になりつつありますが、RF-EFアダプタを使えば、ボディ側がRFマウントでも使用することができる為、今買っても決して後悔しない一本です。
他にも、カメラ機材に関する記事を書いていますので、興味あればご覧になってください。
 14,500ショットしたのでCanon EOS 7D MarkIIを語ります
14,500ショットしたのでCanon EOS 7D MarkIIを語ります
 Tamron 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD for Canon 初めての野鳥撮影望遠ズームレンズ
Tamron 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD for Canon 初めての野鳥撮影望遠ズームレンズ
 Sigma 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Sports テレコンキットで超望遠デビュー!
Sigma 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Sports テレコンキットで超望遠デビュー!
 Sony高画素フルサイズミラーレスILCE-7RM3(α7R III)導入!
Sony高画素フルサイズミラーレスILCE-7RM3(α7R III)導入!
 Sony超望遠レンズ・FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS(SEL200600G)
Sony超望遠レンズ・FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS(SEL200600G)
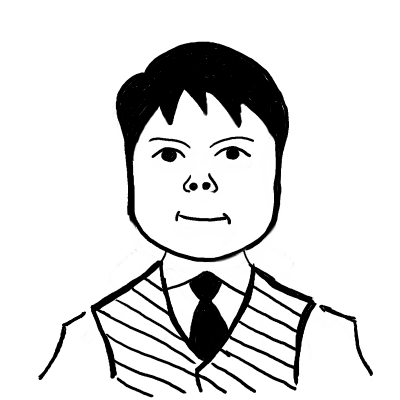 Isamu
Isamu
7DMarkII Canon EF100-400mm EF300mm EF400mmf4 EOSR7 EOS RP FE70-200mm FE200-600mm GRIII ILCE-7M2 ILCE-7RM3 Instagram PENTAX RICOH Sigma150-600mm SNS戦略 Sony Tamron100-400mm α7RIII コンデジ ダム公園 ツキノワグマ ネイチャー フォトコン プリント ミラーレス ミラーレス一眼 ライトアップ レビュー 一眼レフ 仁別 写真 探鳥 春 望遠レンズ 桜 渓流 秋田 紅葉 観光 都市公園 野生鳥獣 野鳥 風景